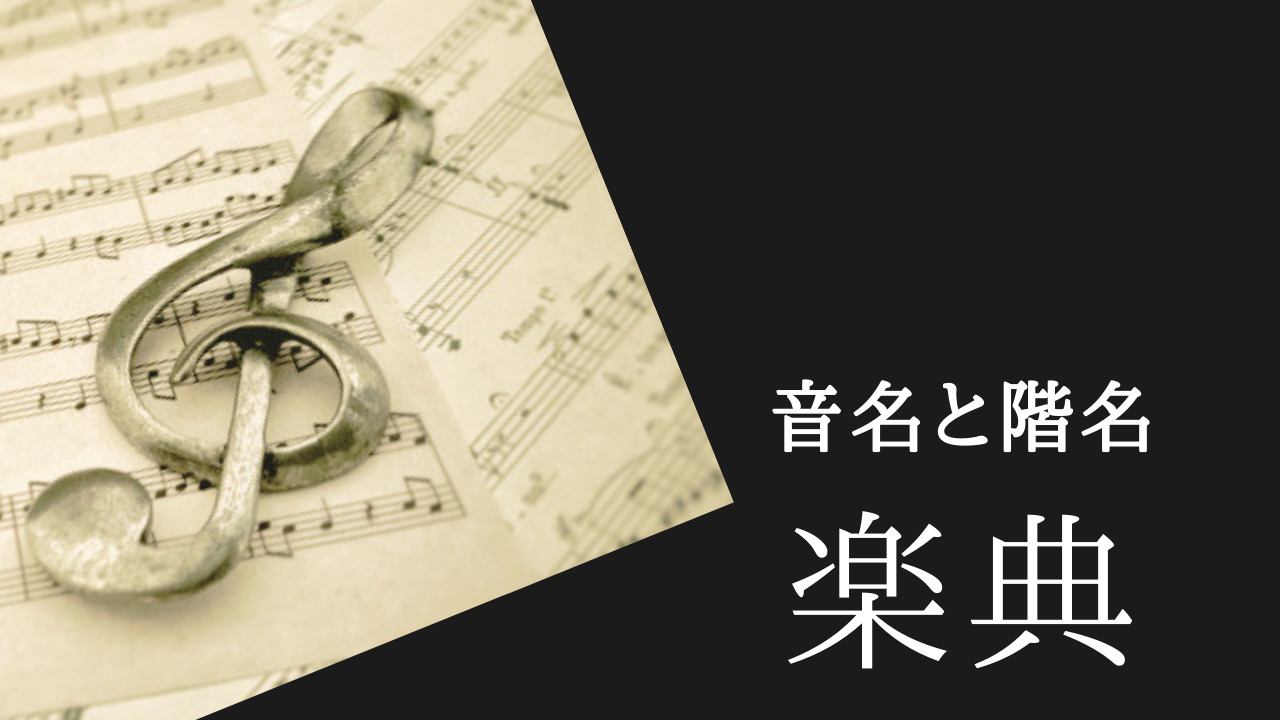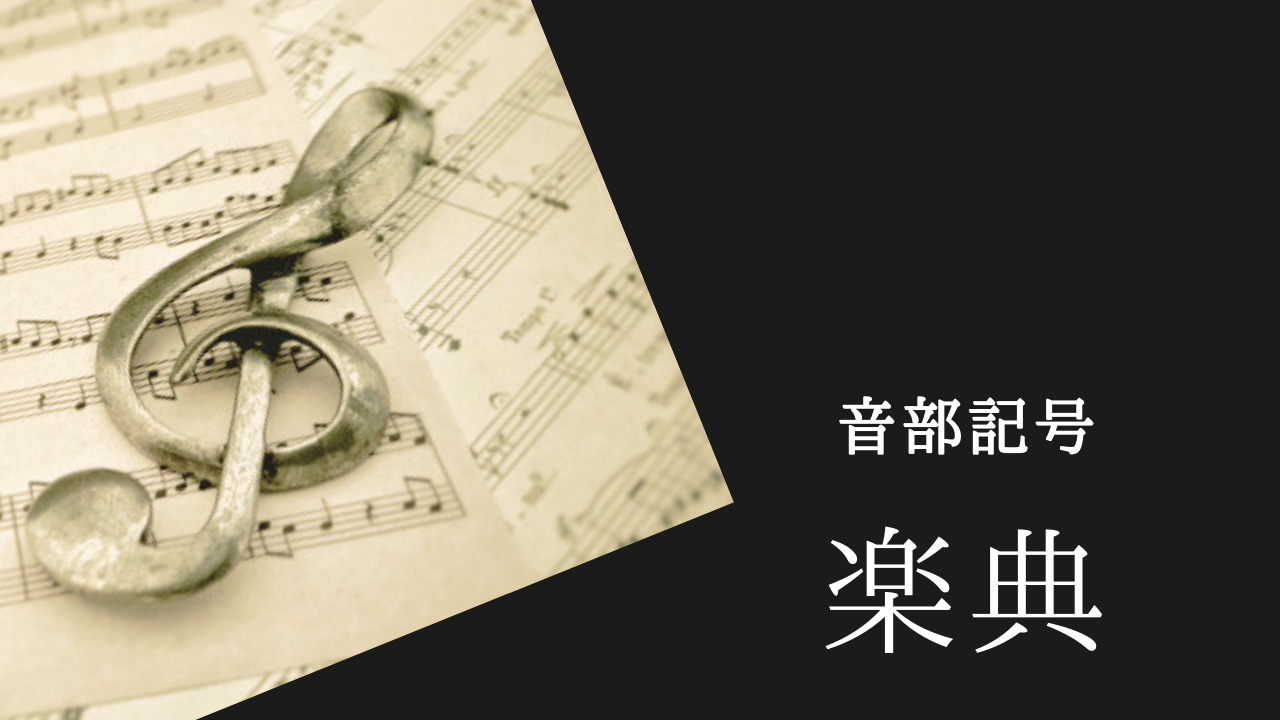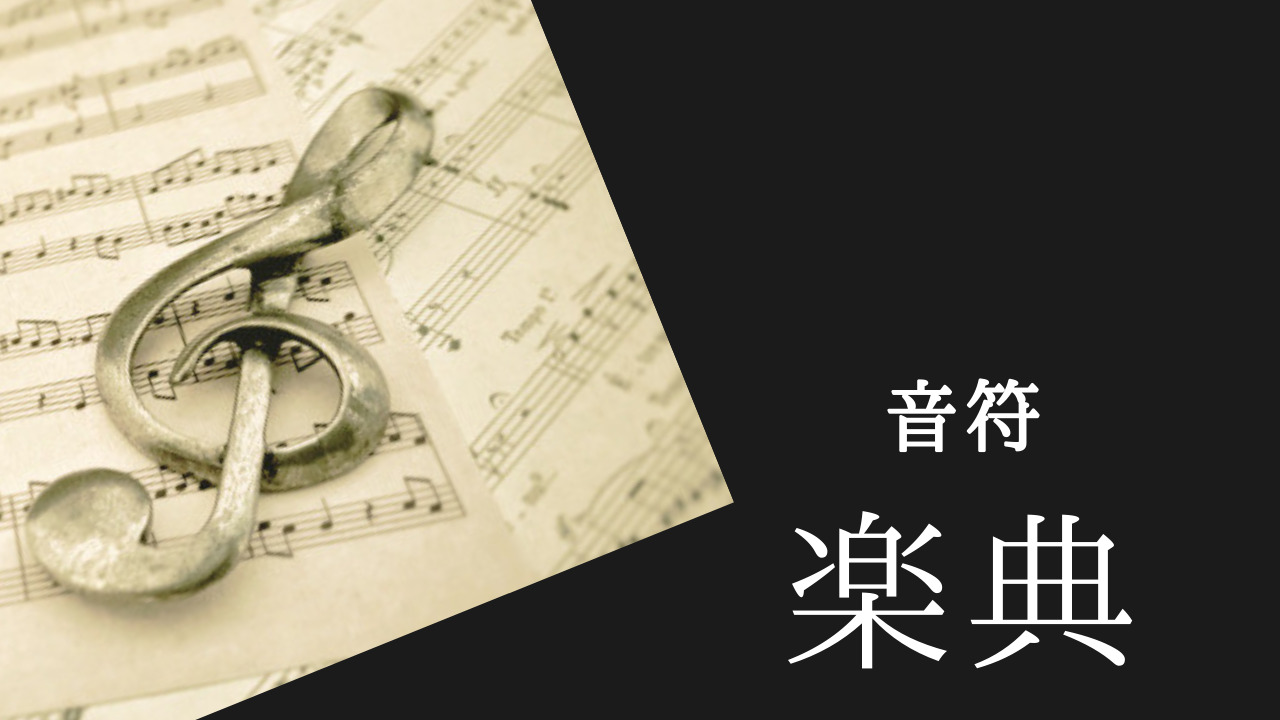こんにちは!
今回は、「音名」と「階名」の意味について説明します!
音の名前と言えば、「ドレミファソラシド」を想像しますよね!
音楽の世界では、「音名」と「階名」という2種類の音の呼び方があります!
「ドレミファソラシド」は「階名」です!
「音名」には、「ハニホヘトイロハ」「CDEFGABC」「CDEFGAHC」という表現方法があります!
今回の記事では、「音名」と「階名」の違いについて詳しくなりましょう!
特に、吹奏楽部で活動している方はしっかり理解していきましょう!
最後まで、是非ご覧ください!
参考にしている書籍はこちら!
「音名」について
まずは、「音名」の意味、呼び方などついて説明していきます!
普段聞いたことがある人は少ないと思いますが、音楽の世界では当たり前のように使われています!
「音名」とは?
「音名」とは、その音の高さに対する固有の名前です!
音そのものについている音の呼び方です!
下の楽譜を見てみましょう。「階名」を表しています!
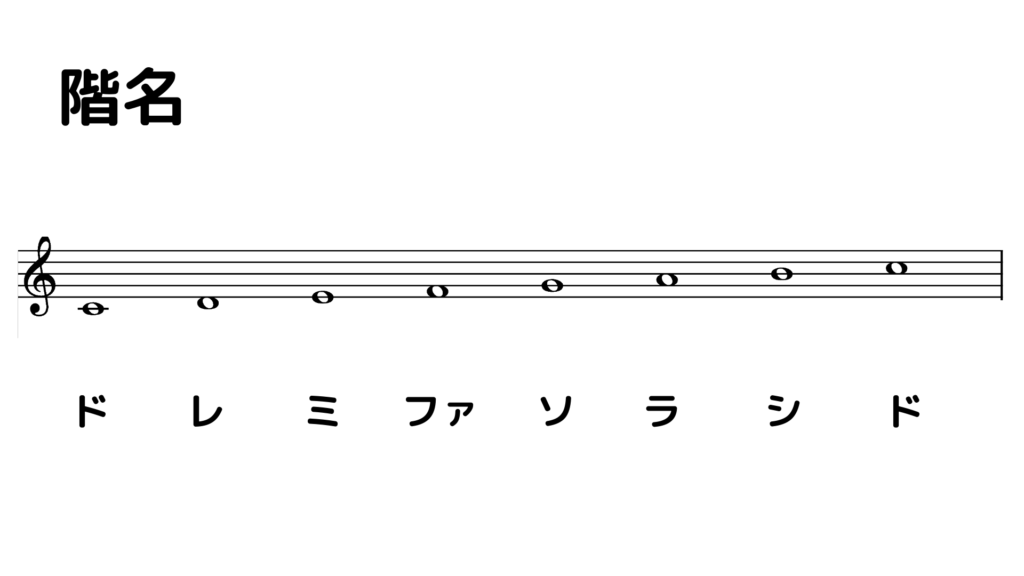
いわゆる普通の(ドレミファソラシド)です!
音楽の授業などでは、このように教えてもらったのではないですか?
これを「音名」で表すと、以下のようになります!
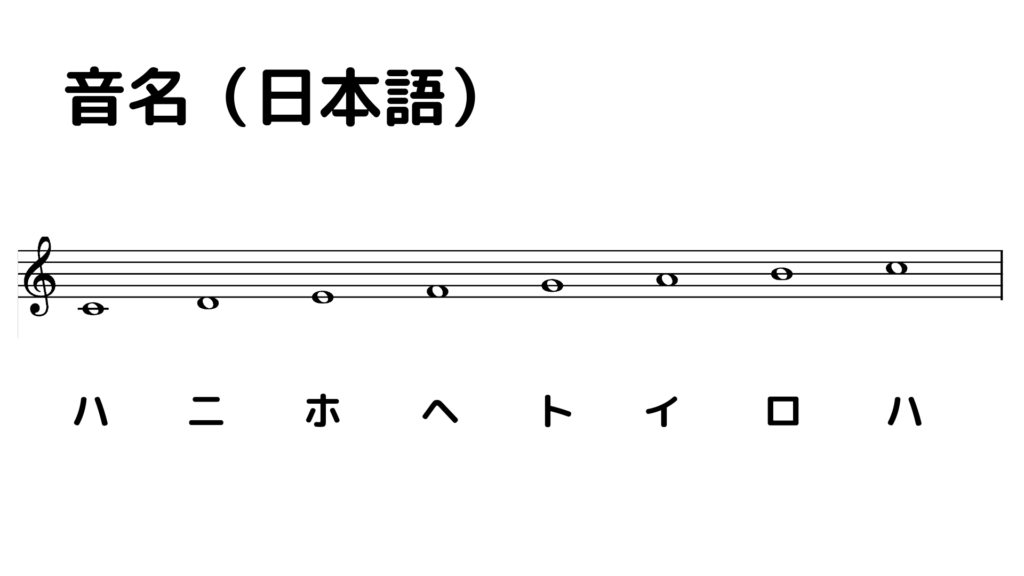
音の高さが同じ場所でも、音の呼び方が違いますね!
オーケストラで演奏される曲などに「ハ長調」のような言葉が使われていますが、
この「ハ」の部分が音名の「ハ」のことなんですね!
「音名」の呼び方
「音名」の考え方は、世界中共通で、日本語以外の読み方もあります!
今回は、音楽業界でよく使用される言語である、英語とドイツ語を紹介します!
特にドイツ語は、馴染みがないと読みにくい言語なので、読み方まで理解しておくと良いでしょう!
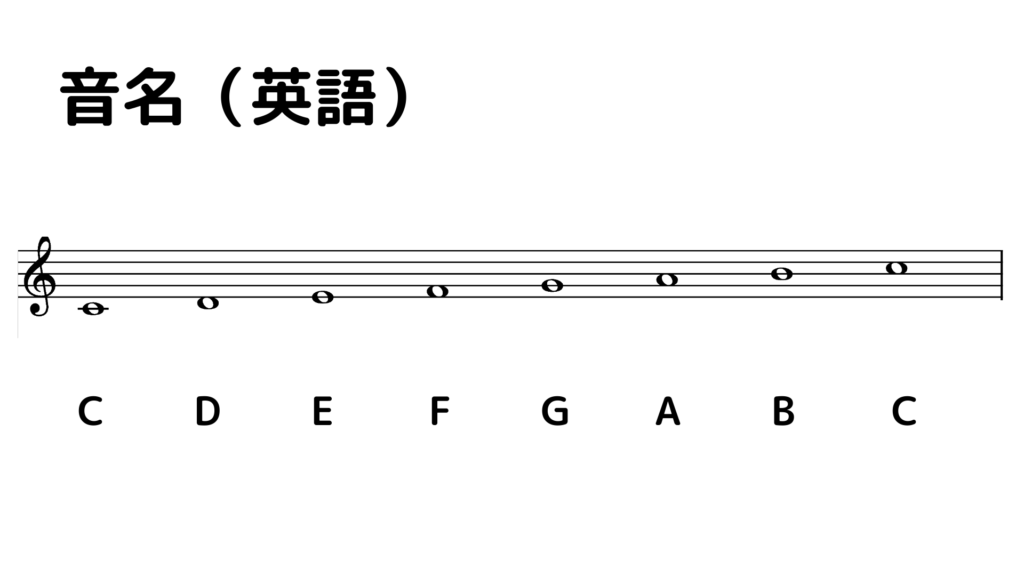
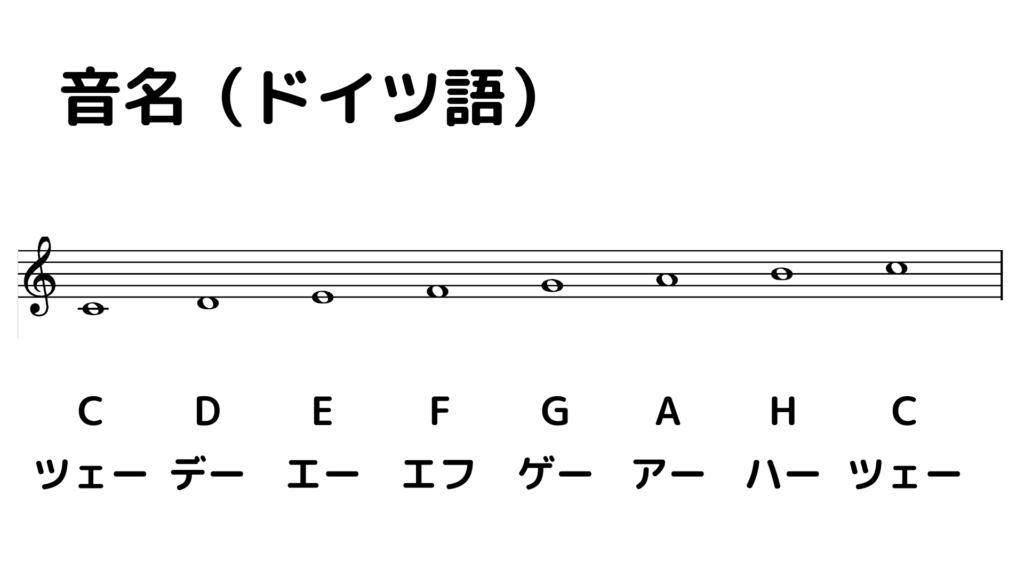
英語とドイツ語では、ほぼ違いはありませんが、英語の「B」の部分は、ドイツ語では「H」になっていますね!
最後に、ここまで紹介した音名をまとめます!
縦に読むと、同じ音に対するそれぞれの言語での呼び方になります!
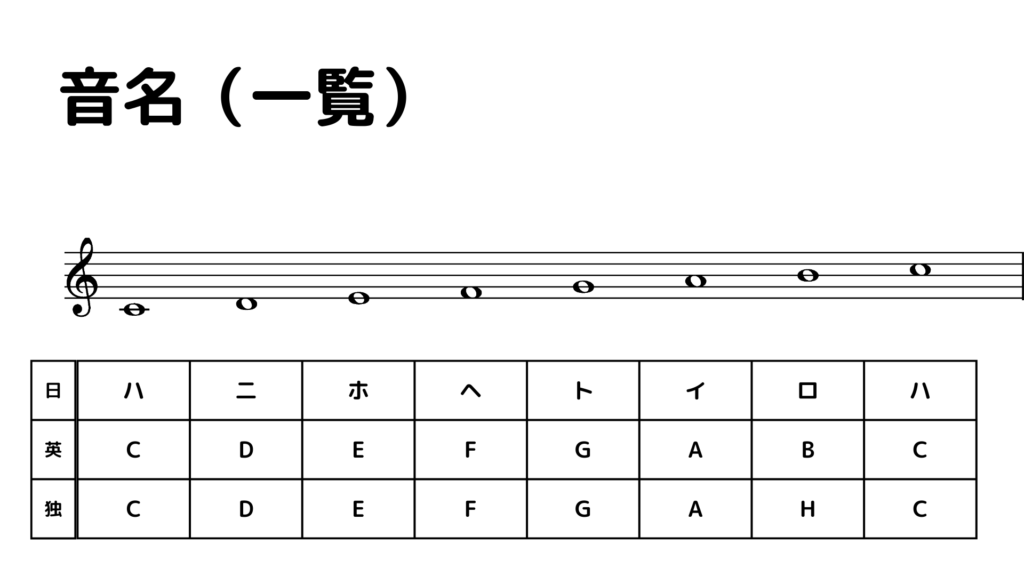
「階名」について
ここまで「音名」が、音固有の名前であると説明してきました!
では、「階名」は一体何の名前なのでしょうか?
「階名」とは?
「階名」は、ある音階において、何番目の音なのかを表す名前です!
「音階」での「名前」と覚えておくといいでしょう!
先ほどの「階名」の楽譜で、説明していきましょう!
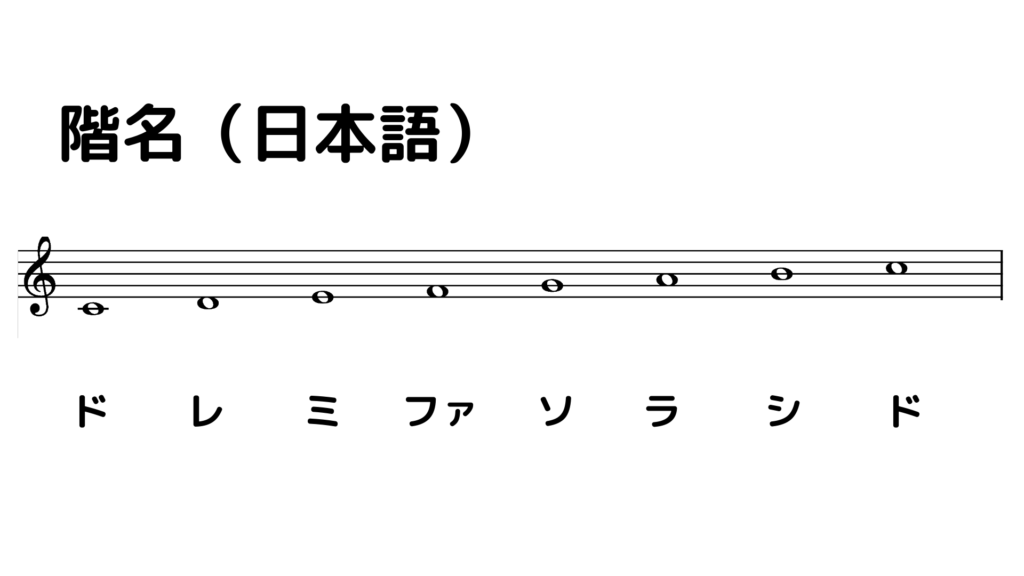
大切なのは、「階名」は、ある音が音階の中で何番目の音かを表しているという点です!
実際は、「階名」を「音名」として扱う場合もある
ここまでの説明の中で、「難しい!」と感じた人もいると思います!
何故なら、現在「階名」は、「音名」のように扱う場合が多いからです!
実際は、「階名」で音が分かれば問題ない場合が多いです!
音楽業界でも、楽譜を見る際には、「ドレミ」で音を判断するのが一般的です!
ですので、下の楽譜のように音を読んでいきましょう!
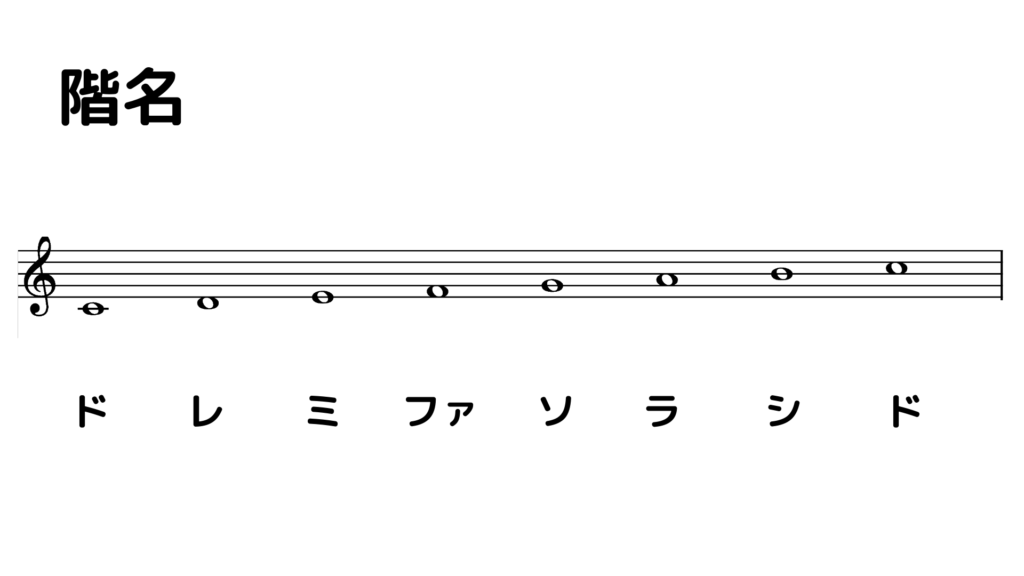
クラリネットやトランペットは、「ド」の音の高さが変わってくる?
しかし、吹奏楽で使用される楽器の場合は、事情が異なります。
自分の楽器の「ド」が何の音になるのか(「音名」だと何になるのか)を確認しましょう!
代表的な楽器と、対応する「ド」は、以下の通りになります! ※英語表記
- フルート、オーボエ、ファゴット・・・「C」
- クラリネット、トランペット、トロンボーン・・・「B♭」
- ホルン、イングリッシュホルン・・・「F」
- アルトサックス、バリトンサックス・・・「E♭」
これらの楽器は、「移調管」と呼ばれる楽器で、それぞれ「ド」の「音名」が異なっています!
「移調管」を演奏すると、「移調管」で演奏する「ド」と、ピアノの鍵盤を見て演奏する「ド」の2つの音の高さが違って聴こえます!
仕組みを理解するには、さまざまな音楽の知識が必要になるため、今回の記事では、次の点を押さえておきましょう!
- 「音名」は、音の高さに対する固有の名前
- 「階名」は、音階の中での順番を表す名前
- 「音名」と「階名」の音の高さは、必ず一致するとは限らない。
まとめ
これまで、「音名」と「階名」について説明しました!
今回の記事では、下記の内容を紹介しました!
- 音の名前には、「音名」と「階名」がある。
- 「音名」は音の高さの固有の名前、「階名」は音階での名前。
- 「ド」が「C」の時もあれば、「F」などの場合もある。
参考にしている書籍はこちら!